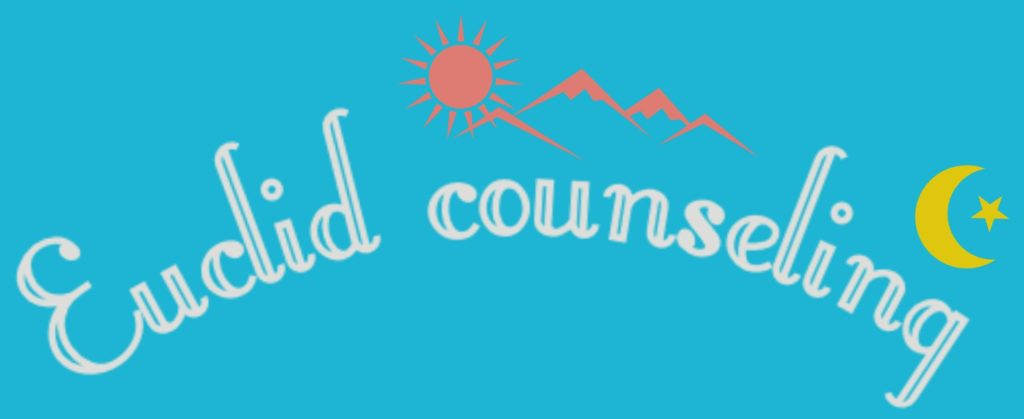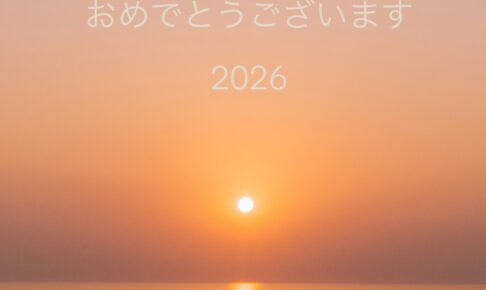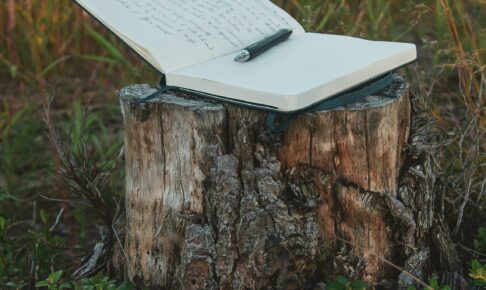生きづらいと困っている人
と
まあまあで妥協しながらも生きていける人はどう違うのか
ということを基に
精神構造が、どうやって出来上がっていくかというところを
ずっと観察してきました
途中経過ながらも
なんとなく傾向としてわかってきたことをここで話してみたいと思っております
私たちは生まれてから
『この世界の構造』を何とかして捉えようとして生きてきます
最初は『泣けば思い通りになる世界』=赤ちゃんとしてお世話される時代
から
『大人として扱われるようになって、思い通りにいかない世界』
への
移行のプロセスがとても大事。
いわば『緩やかな諦め』を何度も繰り返す
傾向と対策の繰り返しで
学習していくと言ってもいいと思います
そこで、ふと気になってきた傾向がありました
それは『願掛け』をするクライエント様が非常に多いということです
この願掛けは
『お星様にお願いする』なんていう可愛らしいものもありますが
今回問題となるのは
どちらかというと切迫した雰囲気を伴う『願掛け』になります
ーーーーーーーーーーーーー
私も小さい頃よくやっていたものとして
幼少期は、田園都市線の線路脇が通学路だったので
いつも電車と競争だ〜とか
あそこの橋を渡るまでに電車が通らなければいいことが起きる
なんてことをしておりました
まあしかし
この、自分で勝手に決めたミッションで勝とうが負けようが
悪いことは起きるし
良いことも起きる
だからそのうちに、この遊びをしても虚しいしつまんない
と辞めてしまったのですが
この遊びの、不思議な引力性みたいなものを
当時から不思議に思っていました
電車が背後からすごい勢いで走ってくるのを
なんとかして、振り切る
という遊びは
身体の中心を非常におかしな感覚に導くと言いますか
切迫した状況を
すぐに、お手軽に作れるのです
この切迫した状況の、なんとなく甘美で興奮する感覚は
他ではなかなか作り出せないものでもありました
しかしこれに
私は違和感と
気持ち悪さを感じたので
数ヶ月ほどで辞めてしまったのですが
自分で悪いことが起きたら
これを相殺するために、何かのミッションをクリアするみたいな勝手な妄想癖や
これをクリアすれば良いことが起きるみたいな
切迫した状況を作り出すものは
今になれば『コントロール欲求』の表れだったのかもしれないなあと思うのです
自分ではどうしようもない不安などに対抗する遊び
・・しかも一抹の快感すら覚えるような感覚
これはすなわちマゾ的なものを呼び覚ますものでもありました
私は小さい時に、また覚えているものがあるのですが
母親が先に歩いて遠ざかってしまう・・という姿を
自分は止まったまま見送るという遊びをする時期がありました
『このままだと置いていかれる』という恐怖感と
それを自分で
解除できるという綱渡り的な一種の快感を伴うような感覚が
同時にくる感覚が
不思議でならなくて
しばらく飽きずにやっていたが
しかしこれもまた、飽きてしまった
何より今となれば
飽き性というのが私の精神構造を助けたのかもしれないが
ーーーーーーーーーーー
クライエント様との話や、周囲の人たちを見るごとに
実は、こういった『密やかな遊び』をしている人が多いということに
気がついたのです
そして、私の見る傾向からすると
この『コントロール遊び』に近しいことをしている人は
ほとんど、強迫的なしんどさを、今も持っているのです
ーーーーーーーーー
強迫的なしんどさとは
『曖昧なままで生きることが難しい』ということです
人は、ものすごく曖昧な生き物です
人だけではなく
地球や
自然
宇宙なんかも、ものすごく曖昧であり流動的なものです
曖昧模糊(アイマイモコ)こそが
私たちの存在でもあり
基盤となるものでもあるのですが
その曖昧さを、コントロールしようとしてしまうのが
強迫的なしんどさでもあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この、ひそやかな戯れとも言える『賭け遊び』にふける子供達の特徴として
安全基地が機能していないという状況があるような気がします
まだまだ少ない臨床の結果から導き出したものでもあるので
これから精査していく必要があるのですが
ほとんど、『親が安全基地』ではなかったというパターンです
・・というより
親も『賭けの対象』となりうるくらいの頼りなさだったと言ってもいいかもしれません
小さな子供にとって
外の世界は、危険で脈絡がなく、弱肉強食で
いつも自分が通用するわけではない
というものですが
自分の中で安全基地が機能していれば
外の世界を
『嫌だな』と思っても良いんだと、切り離せるし
『いや、それでも一緒に遊びたい友達もいるし』と
自分が近寄ったり、遠かったりするうちに
自分の『流動性』をそれなりに認められるようになります
そしてそれは決して本人にとっては悪いことではないのです
しかしそれを体得するには、時間が必要。
だから途中段階として
1人で、世界をコントロールしているという『願掛け』もしくは
『1人儀式』をすることは
不安の回避手段であり、
自己存在の保持のための自衛策でもあるのです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
しかし
『願掛け』とも言える、『1人儀式』は
実は少し不穏な要素を含んでいるところがあるのです
自分では、もしかしたらコントールできないのかもしれないという
世界への恐怖感は
どの子供でも通過儀礼として通るものです
その儀礼中に、『1人儀式』をしている最中に
『自分を生贄』として遊んでしまう場合に、注意が必要なのです
いわば、『魔法』には『生贄』が必要だーーーー。
と思い込んでしまい
世界との密やかなお遊びだったり、賭けだったり儀式だったり
魔法ごっこのようなものが
次第に呪術性を帯びてきて
そして呪いとなってしまう場合があるのです
流れとしては
1. コントロールできない世界に生まれ落ちた
2. でも「自分には力がある」と信じることで自尊心を保った(魔法の誕生)
3. けれど、その「力」は誰にも信じてもらえず、むしろ否定された
否定されたという事実から恥を感じて
それを自分への罰と思い込み
4. 「じゃあ私は“罰を受ける力”しかないんだ」と思い込む
つまり、希望としての魔法 → 罪としての呪いへ転化したというものです
『魔法を欲しがりたい』
それは「世界がどうしようもなく残酷だから
せめてこの手に奇跡を…」っていう祈りにも聞こえたりします
でもその魔法は、自己罰の形でしか行使できなかった
というバージョンにも変わりうるのです
ーーーーーーーーーーーーーー
実際に、魔法らしきものを使える人はいらっしゃいます
しかし、その魔法は『罰を与える』という形では現れません
どちらかというと『啓示』に近しいものだったりして
しかもその啓示を受けるご本人様もいまいち意味が理解できない・・という
パターンが多いのも事実です
また、私が見るに
うちにいらっしゃるクライエント様のほとんどにおかれて
素晴らしい勘が働く魔法使いでいらっしゃいます
みなさま、何かしら
感じてらっしゃる
しかし、魔法も1人儀式もやはり『ものは使いよう』ということで
なんらかの心構えは必要な気がしています
道を外れると
途端に魔法が使えなくなるというのもよくある話。
魔法の使い道は
『矛盾』というものを
『対立』するものではなく
『対となるもの』という感覚で『持つことができる』と間違いがないかなと思われます。
(『魔法』は比喩として使っております)
Instagramはじめました カウンセリングルームの様子を よかったらご覧ください