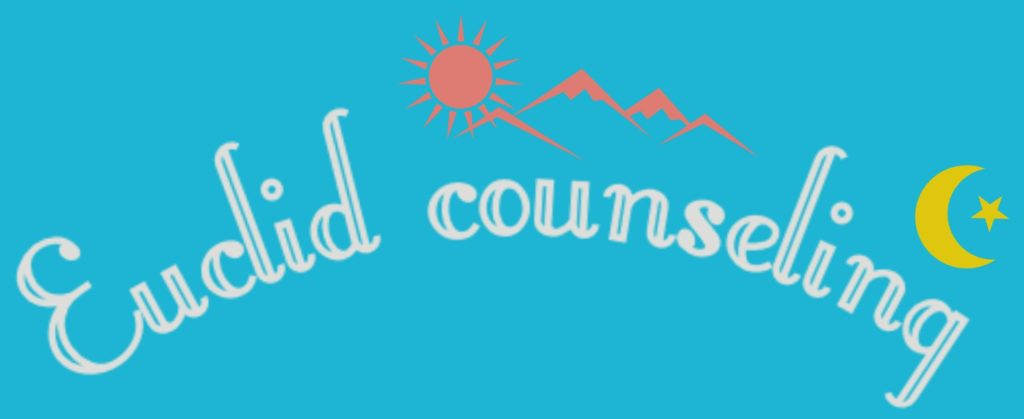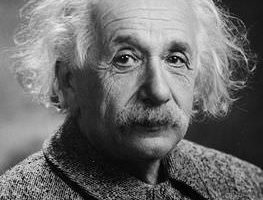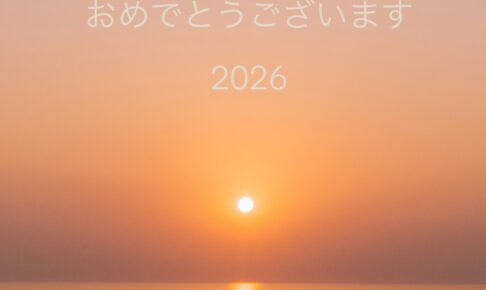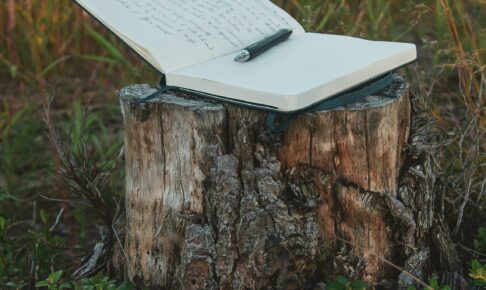劇場型人間
『私はこんなに可哀想なの』
『私ってばいつもこんなに酷い扱いなの』
という舞台から降りてこない人はいるものです
自分の舞台では『本当の私になるために』という劇を
繰り返し繰り返し演じ続けるのです
そして周囲を自分の舞台に引き込んで
自分にスポットライトが当たるように指示をする
何故なら
『自分の思う通りにならないのは他人が私の人生を邪魔をするから』
という舞台を演じている間は
『自分の非を認めずに済むから』
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
カウンセリングでは外在化ということを
テクニックの一つとして用いることがあります
心理学・心理療法における外在化(externalization)とは、
クライアントの中にある“問題”を、その人“自身”と切り離して捉えるテクニックや考え方です
たとえば──
• ✖︎「私は不安な人間だ」
• ✔︎「“不安”というものが私に話しかけてくる」
みたいに、問題を「人格の一部」から「別の存在」にしてあげる方法。
どこで使われるのかというと
主にナラティヴ・セラピー(語りを重視する療法)で使われたりします
認知行動療法(CBT)でもこの方法は用いられていたりします
なぜ外在化するのか?というと
1. 自己否定からの脱出
→ 問題=自分 じゃなくなると、少し楽になる。
→ 「私はダメな人」じゃなくて、「“ダメだ”と感じさせる何か」がある、って考え方に転換できる
2. コントロール感が戻る
→ 「この問題、私が向き合える“相手”なんだ」って感覚になる
→ 対話できる、工夫できる、“距離”ができる
3. 物語が変えられる
→ 「あなたと不安の物語」を、新しい展開に書き換えることができる
→ 例えば「“怒り”に支配されてる男」が、「“怒り”を味方にして動ける人」になったりする
例え話として
想像してみてください
自分の中に「不安」って名前の、ちょっとやかましい妖怪が住んでるとします
その存在が
あなたが何かしようとするたびに「無理!ダメ!やめとけ!」って言ってくる
普通はそれを間に受けて
「私は弱いんだ・・だって不安で動けないし…」って思うものです
でも、外在化のテクニックを使って
考えてみると
「あ、不安が今日も私に声かけてきてる。
相変わらず皮肉たっぷりで元気そうだな。
で、私はどうしたい?」
と、
視点が変わるだけで、
あなた=不安 ではなく
あなた vs 不安 になるのです
つまり、自分が手綱を握れるようなポジションになれるということが
外在化の大きなメリットです
ーーーーーーーしかし
今回はこの外在化が、むしろ状態を悪化させる人というのが
いるというのがブログで書きたいことなのです
それが最初に書いた『劇場型人間』の人へのアプローチとしては
あまり芳しくない(・・というより悪化させる)結果になることが多いということ。
どういうことかと言うと
先ほどから書いている劇場型の人というのは
『演技性人格(障害)』の人のことを指します
劇場型の人というのは
自分の置かれている環境や感情、立場を演出的に表現する傾向があります
何故かというと
『内面の確信』が薄いために
大袈裟に外側で強化しないと、自分という存在が、相手から捨てられてしまうのかも・・という
不安をいつも持っている方々なのです
『内面の確信』とは
『自分の感覚を、自分のものだ』と納得していることです
・・これが好き
・・これは嫌
・・これは怖い
・・これは辛い
など五感に関することから、自分が世界をどう捉えているかということ。
そして内側から出てくる自分の感覚に対して
自分自身で納得していることを『内面の確信』ができていると言います
しかし内面の確信ができていないと
・他人が良いと言っているものが良いもの
・他人が欲しがるものが欲しい
・他人の規範にそのまま乗っかると安心
という他人が決めたものを
自分の中の軸としてしまうという傾向があります
自分の中の基準が無いという状態なので
自分と他人の区別がつきづらく
他人の感情を自分のものとしてしまうというという傾向も出てきます
こういった混乱から
自分自身への適度な信頼感が無いために
自分のことを蜃気楼のように捉えているようで
だから、自分の輪郭を強く周りにアピールするために
どうしても演技がかった振る舞いをしてしまったりするのです
演技と言っても様々な役柄があって
それは好みで選ばれるのだと思うのですが
現代の女性は『か弱い』という役柄を好んで選ぶ傾向にあるようです
それは一番『か弱い役』が得をするからだと思われます
誰かに構ってもらえる
誰かに肩代わりしてもらえる
誰かに気にかけてもらえる
などという旨みがあるから、この役はとても人気です
劇場型でも、『気が強い』なんている役を持っていると
なんだかんだ現状を打破していくので
案外、うまく生きていけたりもするものです
ーーーーーーー
大学や職場なんぞでの話をクライエント様から伺っていると
本当に多くの女性がこの『か弱い役』を欲しがり
そして『か弱い役』同士で潰しあっているところも見られるようです
ーーーーーー
話がそれましたが
この劇場型の人に『外在化』のテクニックを用いると
薬どころか毒☠️の様相を呈します
『私、不安なんです。もう居ても立っても居られない』という方に
『不安があなたの邪魔をするのですね』(外在化)
・・なんていうや否や
『そうなの!私は不安に襲われる可哀想なヒロインなの』という
ヒロインの悲劇性が高まった状態が出来上がります
ポケモンの進化のように
ますますをもって、戦闘力を高めていきます
しかし、周囲からはどう見ても
『・・・そんなに悲劇でもなく無い??』という反応を示されてしまうので
どうにかして自分の悲劇性を認めてもらわないと
周りからの支援が見込めないと焦ってしまうので
もっと強く演技をせざるを得ない状況になってしまうのです
ーーーーーーー
演技性の方の特徴として
細かく内的な感覚を言語化してもらっていく試みをしてみると
案外『語彙』が少ないという傾向が見えてきます
感情を説明する
言葉を多くもっていないのです
なのでいつも一辺倒の説明になってしまい
最初は耳を傾けてくれた周囲も
ありふれた言葉だけを繰り返し聞かされると
つまらなく感じてしまうのは仕方がないことなのかもしれません
次第に離れていく周囲に対して
何故自分から離れて行ってしまうのかを理解できないままでは
余計にストレスなので
『こんな私を放っておく周囲は酷い人だ』
という舞台を作り出し
そしてそこに1人で座り込むしかないのです
ーーーーーーーーーーーーーー
演技性の人ほど、人との触れ合いを望みながらも
不器用な人はおりません
演じているな・・と、見破られる事も多いので距離を置かれてしまいがちなのです
また、演技性の人は『自分の舞台に上がってくれる脇役』を
周りに強要する生き方しか知らない為に
余計に孤独になっていくというジレンマに生きているのです
そういう方へのアプローチとしては
『一度、舞台から降りてもらうしかない』
自分の舞台はまたいずれ何度でも上がれるものです
演技性の人は、他人の舞台を知りません
他人にも、『他人の素晴らしい人生がある』ということに
気が付いていないのです
近所の人
スーパーで働く人
犬を散歩させている人
電車で隣に座った人
日常の一コマとして流しがちな風景でも
実は1人、1人に壮大なドラマがあるものです
人間はどんな人でも、悔しかったり悲しかったり、
誰かを愛おしく思ったり
壊してしまいたいぐらいに恋焦がれたり
狂うぐらいの欲望を感じたりしているものです
そして憂鬱に感じたり
意地悪したり
誰かを傷つけたり
憎んだり
妬んだりもあるものなのです
それを、観客側から眺めてみるということをお勧めします
(注意点としては、その眺めている舞台に自ら登場人物として上がらないこと)
ほら、昔の源氏物語でも
どの殿方も、姫君でも、奥方でも
それぞれに素晴らしい生き様とドラマがありました
それは、決して小説や物語の話ではなく
生き様自体が、どの時代の、どの方もドラマチックであり
そして彩りがあるものです
皆、自分の中の渦巻く感情に翻弄されながらも生きていくというのが
人間なのです
だから、周りに対して
『私の舞台に上がって、私を引き立てて』という強要はあまりにも侵害行為です
だからこそ、一度
自分のお気に入りの舞台から降りて
他人の舞台を観察してくる!という冒険に出なければならないのです
面白いことに
自分の舞台から恐る恐る、降りてみると
最初に出会うのは『かつての自分』と恐ろしく似ている人に
出会うということです
演技性人格障害の人が
かつて自分もそうだった
『スポットライトを浴びたがっている人』に出会った時は
とても批判的になりがちです
自分と同じ、スポットライトを欲している人に出会うのは
非常に苦痛でもありますが
それは、かつての自分への決別の一歩でもあります
そこで最初に上がる幕は
『自分の影との出会い』とでも言いましょうか
その幕間は、決して逃げてはなりません
その幕間こそ、物語の始まりでもあります
自分で、自分が気にいる台本を作っていたあの頃とは違い
他人に翻弄されるという
台本なしの舞台は非常にドラマチックです
そしてそこで感じたことは、いずれ自分の宝物や結晶となります
『誰か私を光らせてよ』と原石のまま座り込んでいた存在が
もう、削られ
研磨され、剥がされていくのです
そこで、むき身の自分を感じて
きちんと悔しさや悲しさや
等身大の自分を見れることで
いかに昔は、自分は受け身だったのか・・
そして受け身なのに、周囲に強要していたのか・・
という裸の王様を感じるのです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この『裸の王様』のような恥ずかしさは
痛みを伴いますが、成長として大切なプロセスです
幼児的万能感を手放すのは
この『裸の王様』の恥ずかしさを知って成長するものです
なので、どなたも通る道です
それを、演技性の人は
少し遅れて感じているだけなので
『自分って、こんなに恥ずかしい人間なんだ・・・』なんていう
憐憫に浸らなくて大丈夫です
その恥ずかしさは普通のことです
どのひとも、もれなく通過したものです
なのでありふれたものです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そんな、こんなを通じて
他人の舞台なんかも鑑賞しつつ、
いかに自分が自分の舞台にこだわっていたのかを理解してきた頃
それと同時に
『周囲との協調』が生まれ始めます
他人との距離感が程よくなり
話が弾んだり
安心できる対話ができるようになってきたりと
自分で、自分の人生をお膳立てしなくても
ゆるりと
周囲との関係性を楽しむことができるようになります
まるで禅問答のようですが
『自分がお膳立てする人生』を手放していくに連れて
『もっと大きな舞台』に自分は既に参加していたんじゃないか!
みたいな感覚が生まれ始めてきます
Instagramはじめました カウンセリングルームの様子を よかったらご覧ください