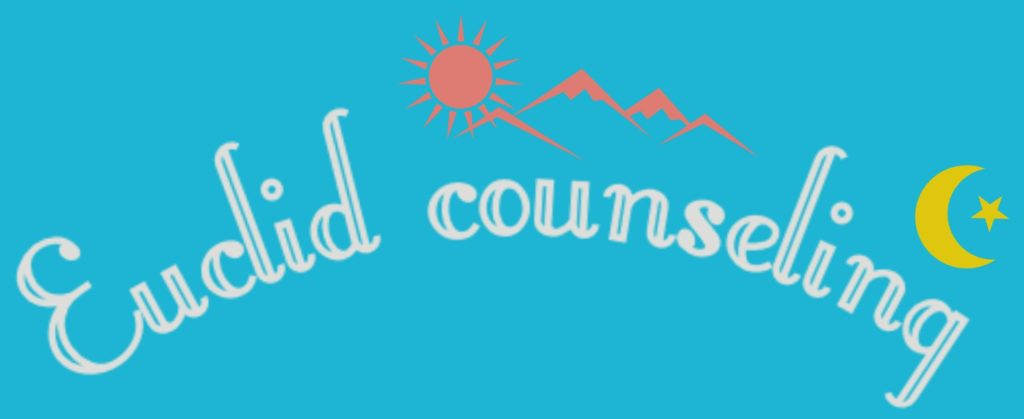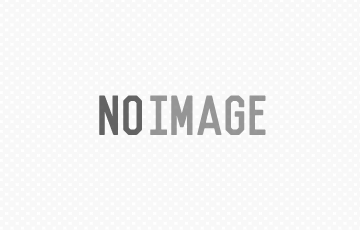『鬼』という概念を用いてカウンセリングを進める時があります
これはクライエント様からの意向があった場合なと状況によりますが
大抵、『生活でうまくいかないところがある』という悩みから
結果的に自分の中の『鬼』と向き合わざるを得ないというときに
出てくるものです
『鬼』と書いておりますが
これは私の師が用いていた言葉でもあり
そのままここでは引用していますが
現代風に言うなれば
『疾病利得』や『支配性』
そして『コントロール欲求』などに当てはまるでしょうか
カウンセリングとして、直接的に『疾病利得』などの言葉を用いるのは
私はあまり好みではないので
神話や物語の中に出てきた言葉などを用いて
カウンセリングを進めていきます
例えば『天邪鬼』とかなんかもそうです
心の動きを表すものとして表現しているもので
それは怪物としての姿ではなく
人の心に潜む影として 私には映っています
さて
妖怪や物の怪は 山や川や風の中から生まれます
自然界の不可思議な気配が姿をとったもの
しかし『鬼』はもっと人間に近く
怒りや嫉妬 執着や依存 といったように「手放せないもの」
また悲しみの変幻としても立ち昇ってくるような気がします
余談になりますが
例えば古の物語に見る鬼がいます
古事記には「鬼」という言葉そのものは多く出ておりません
しかし「荒ぶる神」「禍つ神」として 人を惑わせ災いをもたらす存在が語られています
時に人を襲い 喰らう存在として描かれる姿は 鬼の原型になったものなのかもしれません
また
百人一首をひもとけば 鬼は恋の執着や恨みの象徴として顔を出します
夜ごとに忍び込む恐れ 妬みや苦しみの情念が「鬼のように」と詠まれる
鬼は人間の外にいる怪物ではなく 内に巣食う情念の表れとして読まれています
個人的に
男性の訪れを待つしかないという女性の、気も狂わんばかりの苦しさは
大変だったろうなあと思います
そして鬼と臨床の現場に話は戻りますが
カウンセリングの場で 私は鬼らしきものと出会います
そこには「疾病利得」という構造が働いていたり
病や悩みを抱えることで 同情や特別扱いを得る
それは苦痛であると同時に 甘美な利益であり 手放されにくいものです
自分の中の鬼を直視することは痛みを伴うものです
しかし「鬼は確かに自分の中にいる」と認める瞬間から
緊張と依存はほどけ
それまでの緊迫した雰囲気がゆるむのです
鬼は倒すものではなく 共に生きるものなのだろうなと思います
誰にでも
やはり『鬼』は居るのです
でもそれを恐れるでもなく
しかし居ることを認め
そことどう共存していくか 折り合いをつけていくか
・・が人間の『道』なのだと思います
それが周りの人のことも尊重することとなり
お互いに健闘を讃え
そして慈しみあい 癒し合う
という関わりができて初めて
最初に望んでいた『周囲との協調』などのものが
違った形ではありますが 『訪れる』ということになります
鬼と一緒になって『支配する』形では、
『協調』や『安心感』は得られないかなと感じています
ーーーーーーーーーー
しかしこの『鬼だし』は以前からふんだんにブログで書いてきましたが
ものすごくこちらもエネルギーを使うのです
絶対にいい方向に進むのはわかるのですが
いかんせん
私が非常に疲弊している
結局カウンセラーも痛みを伴うのです
何故ならクライエント様の中にある『鬼』からものすごい反発を
そのまま受けるからです
なので自分のバランスがとても大切。
しかし面白いことに
こちらが深追いしないとわかるや否や
わざと鬼が姿を現したりするのです
まるで『捕まえてみな』とばかりです
それでも追わないと、今度は鬼が地団駄を踏み始めます
怒り狂って
あの手この手で
なんとか相手を土俵に上げようとするのです
何気に大変です
ーーーーーーさて
鬼と評した自分の中の『支配欲』やら『自己憐憫』などが
表に出てきたときに
私は最初はもちろん、『対話』を望んでいます
『鬼』の話をとことん聴く
そしてこちらも話をする
話せば理解する『鬼』はたくさんいらっしゃるのですよ・・・!
ご本人が『鬼』を神聖化も異端視もせずに
忌み嫌わずに
まっすぐ見ることができるようになった瞬間
鬼は『守護神』のようなポジションに変わります
「鬼がいたから ここまで生きてこれたのかもしれない」
そんな冗談を交わせるとき 鬼はもう、かつての『鬼』ではありません
ただそこに静かに座って 私たちを見ているように思えるのです
鬼をカウンセラーとクライエント様と
2人で静かに眺めるときに
必ず、ご自分の健闘を讃える言葉が自然とクライエント様からこぼれます
自分自身を
ねぎらう言葉が出るのです
さてもう一つの余談となりますが八尾比丘尼という存在をご存知でしょうか
日本の伝説には 鬼と同じく『人の境界を越えた存在』が語られてきています
八尾比丘尼は
人魚の肉を誤って食べてしまい
不老不死となり 八百年を生きたと伝えられています
そもそも人魚の肉を狙っていた人たちがいるわけなのですが
私はこれらに鬼と同じ「恐れ」を感じたりもするのです
本来人間は死ぬ存在であるはずなのに
死ぬことに恐れがある
しかし結果的に
死なない身体になってしまうと
不死であることが かえって人を不安にさせたりもする
不老不死は祝福ではなく 呪いです
だからこそ人々はそれを「鬼的なもの」として恐れ 敬い 物語に残したのでしょうか
現代に見る鬼的存在
手塚治虫の『火の鳥』の中にも 八尾比丘尼のような存在が描かれています
八尾比丘尼は日本の伝承の中でもとりわけ不思議な存在です
生き続けることの苦しみ
終わりを迎えられないことの苦悩
そこには『鬼』らしきものに翻弄された女性の物語です
結果的に八尾比丘尼は
出家して尼になり、各地の農業や医療を支えていましたが
生きたまま瞑想状態でみずから穴に入り、今も生きているのかも・・という伝説が
日本各地に語られています
鬼とは時代ごとに姿を変えたりします
古事記では荒ぶる神
百人一首では恋の執着
伝説では不死の比丘尼をめぐる物語
現代では人を支配する依存や執着の構造
しかしどの姿にも共通しているのは「人間の限界を超えたいという欲求と恐れ」から
立ち上るものなのかもしれません
さて
鬼と人間らしさの考察ですが
――鬼とは恐怖の象徴か
それとも人を支える媒介なのか
私はまだ答えを持っていません
ただ一つ確かなのは
鬼をめぐって生まれる物語には深い敬意があり
それを巡る苦悩や慈しみなど、それこそが人間らしさであるということです
鬼がいるから 人は自分を知る
鬼がいるから 他者を知る
そして笑い合う
鬼は私たちを苦しめもしますが
しかし鬼を通して 人は豊かで美しい物語を紡ぎ続けてきたのも事実です
古代から現代まで そしてこれからも。
Instagramはじめました カウンセリングルームの様子を よかったらご覧ください