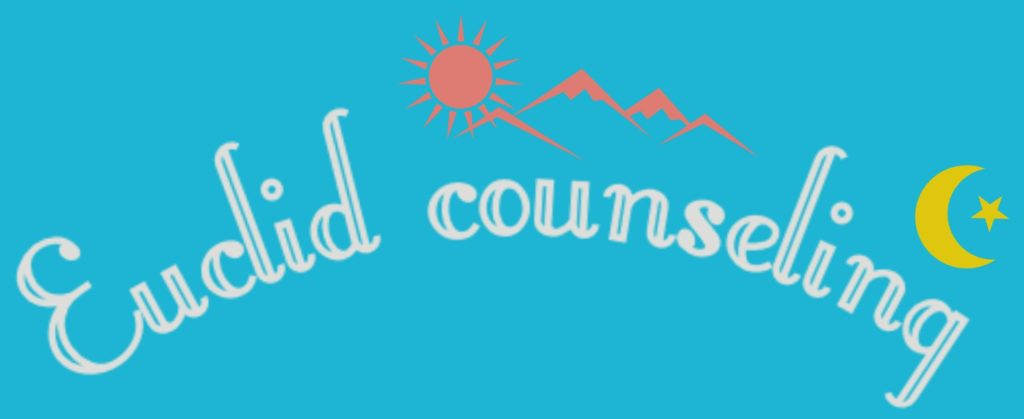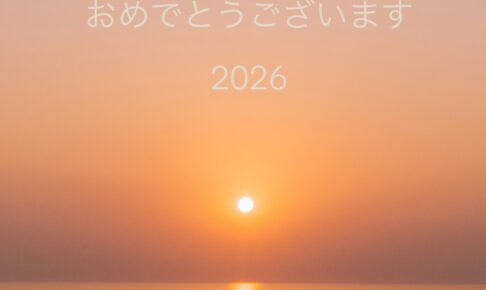トラウマを負いやすい人の特徴というものはあるのでしょうか
それは心が弱いからではなく、深く感じる力があるからだと
考えています
そもそもトラウマは単発なのか
複合的なものを言うのかでも論議が起こるところです
(複雑性PTSDなどは長期にわたる虐待の後遺症と言われていますが
その話はまた今度にするとして)
今日は「トラウマを負いやすい人」について、少し丁寧に考えてみたいと思います
カウンセリングの現場でもよく出てくるテーマですし、
ご自身や身近な人を思い浮かべながら読んでいただけたらうれしいです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まず第一に『トラウマを負いやすい人』として考えるのは
『感受性が高く、繊細なこころを持っている人』
• 音や光、においなど五感に敏感
• 他人の感情にすぐに気づいてしまう
• 「空気を読む」ことが無意識にできてしまう
外からの刺激を受け取りやすく、ちょっとした否定や無視も心の奥深くに突き刺さってしまうことがある人です
感受性が高いことは「優しさ」や「共感力の高さ」の裏返しなのですが
同時に「傷つきやすさ」とも隣り合わせとなっています
体感覚で物事を捉えやすく
相手(虐待者)の感情などにも同調しやすく
余計にダメージを負いやすいです
(これは卵が先かひよこが先かという話でもあって
トラウマを負った結果過敏になるということもありますが)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第二としては
『安心できる関係(安全基地)が育ちにくかった人』
• 幼少期、親や養育者の顔色をうかがっていた
• 甘えたり頼ったりすることができなかった
• 「いい子」でいなければ愛されないと感じていた
このような背景を持つ方は、心の中に「いつでも戻れる場所」が育ちにくくなります
『いつでも戻れる場所』とは
温かな、受け入れられた経験から出来上がる仮想イメージです
『根拠のない自信』と言われることもある場所です
そんな場所が無いことは
ストレスや衝撃を受けたときに自分の中で回復する場所が無いため
抵抗力(レジリエンス)が働きにくくなり、トラウマが「蓄積」されやすくなってしまいます
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第三としては
『他人との境界があいまいになりやすい人』
• 相手の感情や不調を「自分のもの」のように感じてしまう
• 頼まれると断れない
• 自分が傷ついたのに、相手の事情をまず考えてしまう
このように自己と他者の境界があいまいな人は、相手からの言動を強く自分事として受け止め、攻撃や支配にも気づかず耐えてしまうことがあります
これもまた、トラウマが「形を変えて積み重なる」背景になり得ます
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第四は
『自責感や羞恥感を抱きやすい人』
• 「私が悪い」「私さえ我慢すれば」と思ってしまう
• 何か起きた時に、まず自分を責める
• 弱さやつらさを人に見せることが苦手
本当は被害を受けていたとしても、「自分が悪いから」と感じてしまう人です
そのため、助けを求められず、心の中で凍りついたまま、傷が深まってしまうことがあります
『恥』と言うものは他人からの目線が注がれて
初めて成立するものです
他人が、自分に注ぐ眼差しにより
自分の中に『恥ずかしさ』が起こるという仕組みは
果たして本人の問題なのか
その眼差しを持つ人の問題なのか、これも議論の余地があります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第五としては
『過去に未処理のトラウマがある』
• 幼少期の虐待やネグレクト
• 家族の病気や事故、離別などの喪失体験
• 学校や家庭での慢性的ないじめや否定的体験
これらの体験が十分に癒されていないと、新たなストレスや人間関係で再び似たような痛みが呼び起こされる(再演)があります
なぜ『再演』が起こってしまうのかというと
私なりの解釈では
『無意識が傷つきを癒そうとする為に、あえて同じような舞台を設定してしまう』
というメカニズムがありそうです
「何度も同じようなことで傷ついてしまう」という人は、この影響を受けているかもしれません
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トラウマを負いやすい人は
人情味と、優しさを抱えて生きてきた人だと感じています
もしも自分のことを「私はトラウマを抱えやすいかも」と思ったとしても
それは「弱い」からでも「変だから」でもないと思います
むしろ、他人の気持ちに敏感で、自分を責めてしまうくらい、
真面目で、寄り添うことのできる人なのだと思っています
しかし、トラウマを抱えて生きるということはとても辛いことです
ですので
何より大切なのは
「傷ついたあなた」にやさしくなれること
「傷ついた過去」を誰かと一緒に眺めなおすこと
その第一歩が、癒しの入り口になります
『トラウマを治す』と、私もよく言葉にしてしまっていますが
トラウマとは治すものというよりも
『癒す』ものとして捉えた方がわかりやすいかもしれません
完璧に治ることはないですが
しかし、癒えることにより
前よりも格段に、物事への眼差しは深まり
静かで本質を見極めることができるようになると
クライエント様を見ていていつも感じるのです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
補足にはなりますが
神経系から見るトラウマ反応の話を少しだけ。
トラウマ反応を「神経系の視点」からやさしくひもといてみたいと思います
心理の世界では近年、「ポリヴェーガル理論」という新しい神経理論が注目されています
これは、トラウマの反応が“心の弱さ”ではなく、
“神経の防御反応”であることを教えてくれる、大切な視点です
ポリヴェーガル理論は、アメリカの神経科学者スティーブン・ポージェス博士によって提唱された理論です
彼は「迷走神経(ヴェーガス神経)」に注目して
私たちの神経系がどのように安全を感じたり、危険を察知して反応したりするかを、体系的に説明しました
神経の働きは大きく三つに分けられて
以下のようになっています
神経のモード 反応 状態
① 背側迷走神経(フリーズ) 身体が凍りつく、感覚の遮断、無感覚、うつ 「危険が大きすぎて逃げることもできない」状態
② 交感神経(ファイト/フライト) 攻撃、怒り、不安、緊張 「危険に対処しようとしている」状態
③ 腹側迷走神経(安全・つながり) 安心、落ち着き、共感、好奇心 「安全と感じ、他者とつながれる」状態
たとえば、あなたが過去に「大きな怒鳴り声」や「暴力的な場面」にさらされたとします
その記憶が、無意識のうちに神経に刻み込まれていると、似たような音や表情を見たときに、神経が過去の危険と勘違いしてしまうことがあります。
そのとき私たちは…
• 突然動けなくなったり(フリーズ)
• 怒りや不安が高まったり(ファイト/フライト)
• 相手の顔色をうかがいすぎたり
• 会話が頭に入らなかったり
…というような反応を起こします
これは「おかしなこと」ではなく、神経が“あなたを守ろうとして”反応しているのです
しかし今、その学習してしまった神経反応が今の関係を難しくしていることもあるのです
現代の生活の中で、このような神経反応が無意識に作動してしまうと…
• パートナーや子どもとの関係で「突然怒ってしまう」
• 「なんでもない一言」が心に突き刺さる
• 安心したいのに、誰も信じられない
• つながりたいのに、逃げたくなる
というジレンマが生まれます
これは「安全ではないと感じている神経のSOS」です。
⸻
回復の鍵は「安全」な体験の積み重ねからできます
ポリヴェーガル理論では、神経系の回復のために「安全の再体験」が重要だとされています
たとえば…
• 誰かと穏やかに目を合わせる
• ゆっくりした呼吸に意識を向ける
• 安心できる場所に身を置く
• やさしい声に耳を傾ける
• 心地よい音楽、香り、触覚に包まれる
こういった五感を通じて安全を感じることが、神経の再調整を助けてくれます
しかし 「感じること」が怖いとおっしゃる人もいます
もし自分が、「落ち着こうとしても体がピリピリしてしまう」「人といても緊張が抜けない」という状態にあるとしたら
それは心が弱いのではなく、あなたの神経が今も過去の戦場でがんばっているだけかもしれません。
ゆっくりでいいのです
安心の神経は、一夜にして育つものではありません
神経系への治癒の一つとして
ソマティック・エクスペリエンシング(SE)という方法があります
身体志向アプローチです
トラウマケアにおいて
言葉だけでなく身体の感覚にアプローチする療法が近年どんどん出てきています
その代表格がソマティック・エクスペリエンシング(Somatic Experiencing / SE)です
• 記憶を“再体験”させるのではなく、“今ここ”で身体に起きている微細な感覚に焦点を当てる
• フラッシュバックなどの再トラウマ化を避けながら、少しずつ「安全な神経反応」へ導く
• 自律神経の“未完了の反応”を完了させることで、身体が自己調整する力を回復させる
この方法は、言葉ではうまく表現できない苦しみに対して、身体という入り口からやさしくアクセスする道です
私のカウンセリングも、これに近いものを少し用いて進めていく段階があります
カウンセリングの現場では、「なぜこの人は突然怒るのか」「なぜつながろうとしながら逃げるのか」という問いに直面することがあります
その答えが、「神経系の反応」として見えてくると、自分への在り方もやわらかく、そして深くなります
神経系を理解することで
• 相手の反応を“パーソナリティ”ではなく“生理的防衛”として理解できる
• 「変わらない人」ではなく、「安心をまだ十分に経験できていない人」として見られる
• セラピスト自身の“逆転移”にもやさしく気づけるようになる
神経系の知識は、共感の精度を上げ、ジャッジせずに寄り添う支えになります
自分自信が「いま、どのモードにいるのか?」をじっと優しく観察することが大事です
そして自分の言葉や沈黙、まなざし、場のトーンが
どう選び取られているかに気がつくことが、
トラウマの回復には非常に強い軸となります
トラウマを癒すためのポリヴェーガル理論は
自分の神経系という地図を手にしながら
自分自身や他者とのつながりを深めていくための、やさしい羅針盤のようなものです
もし気になるようでしたらお声がけくださいませ
Instagramはじめました カウンセリングルームの様子を よかったらご覧ください