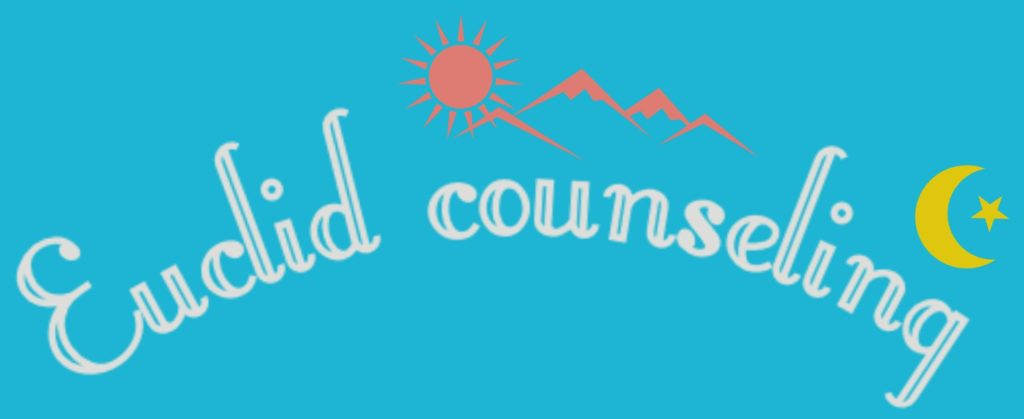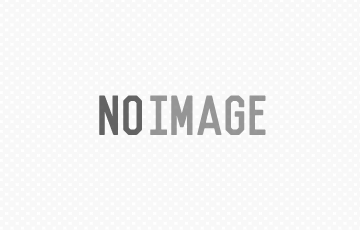「自我防壁」という言葉は、
精神分析的な用語では「防衛機制(defense mechanism)」とほぼ同じ意味で使われることがあります
自我防壁(ego defense / ego wall)とは、外界からのストレスや心の中の葛藤・不安に対して、自我が自分を守るために働かせる心理的な壁や仕組みのことです
代表的なものに「抑圧」「否認」「投影」「解離」「反動形成」などがありまして
心理的に圧倒されないようにするための 「無意識の工夫」 です
たとえば、砦や城壁のように「自我を守る壁」と考えると分かりやすいです
『攻撃から守ってくれる → 生き延びるために必要』
しかし、壁が厚すぎると → 他人との関係が遠くなる、自分の感情も分からなくなるという
弊害が生じ始めます
私のケースで考えると
「怒り」や「惨めさ」を幼少期に捨てたという実感がありますが
その感情を出すと生き残れなかった状況があったため、防衛壁の内側に閉じ込めました(抑圧+解離)
そうすることで自我は崩壊せずに守られたというメリットがあります
しかし、今になって「感情がない自分」「哀しみ怒りだけが残る自分」として生きにくさも出てきたり
また自我防壁のシステムがあまりにも
強固であったり、
また都合が良い(例えば私の場合、何も感じなければそれはそれで静かな場所に沈んでられる)
というメリットがある場合に
なかなか、その防壁を破ってまで生きようとはしないということが出てきます
防壁を破られようとする外界からの刺激に対しては
ものすごく反応してしまい
ますます防壁の中に沈み込むということもあります
今回は、そんな防壁のお話。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この自我防壁というものを
二十世紀の巨匠の2人、フロイトとユングは少し異なる目線から
それを眺めておりました
フロイト的に見ると
フロイトは「防衛機制」を自我の働きとして捉えました
不安や衝動に押し潰されないように、心の中に“壁”をつくって感情や欲望を処理するもの、
つまり「自我防壁」は個人的に作り上げた心の中での壁であり
構造論のイメージで自分の中を眺めてみると非常にわかりやすいものです
一方のユング的に見ると
ユングは「自我」を意識の中心としながらも、それは「自己(Self)」という全体のほんの一部だと考えました
自我が外界や無意識から守ろうとする壁は、実は「集合的無意識」や「元型」から私たちを遮るものでもある
だから「壁が厚すぎると、曼荼羅的な全体性に触れられなくなる」という危うさもある
というものです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クライエント様の最終的な望みをお伺いすると
どのかたも『人と人の間で生きていくために、不安などを取り除きたい』
ということに尽きるのではないかと思うのですが
この自我防壁を
どう扱うか・・ということが
最終的な『門』と言いますか
その門は、開かれている
しかし門をくぐって出るのかどうかは自分次第
というような感覚を受けるのです
• フロイト的な「個人を守る壁」
• ユング的な「全体とのつながりを遮る壁」
この両方を、『自我防壁』という言葉から感じ取るのです
実際に
クライエント様に中にある
防衛の数々・・例えば否認や抑圧や・・などが
それこそフッと取り払われる瞬間に
門が開かれるといいますか
その方を取り巻く世界が全く変わるのです
まるで
世界が温かく
そして柔らかなものとして
その方の前に広がっていくのです
そして実際にクライエント様も
その世界で、かつて自分がしたかったことへの再挑戦や
新しいチャレンジなどが
『今ならできる』
という感覚になるのだと言います
しかしその防壁自体が
今もその方自身を『守る』ために機能し続けているのであれば
その防壁はまだ必要なものなのです
そこの見極めがとても難しくあるところです
しかし、外の世界からは
たくさんの人からのノックがされている状態です
外の人たちは、壁の内側にいる方に関わりたい
その外側からノックする方々は
今関わっている人だけではなく
未来に関わるであろう人たちからも『ノック』されているのが
非常に不思議なところだなあと思うのですが
まるで未来からの時間に引っ張られているかの如く
未来から門が開くようにと
すごい勢いで門が変化していくということも
よくあります
・・これはユングがよくいう『共時性』が出てくる時の兆候です
いわゆるシンクロニシティ
『偶然は必然である』は
未来から、もう問答無用で
『壁を取り払えぃ!!』みたいな
そんな呼び声がかかる時があるのです
未来から呼び声がかかるにはどうしたら良いのかということですが
まずは『しっかりとした望み』を持つことかなと思っております
確実な望みです
確実な望みとは
『どんな感情の自分になりたいか』ということを
しっかり確信することです
どんな方でも
『不安定な自分の感情になりたい』とは言わないはずです
ほとんどの方が
『安心した感情を持ち続けたい』に近いにものを
願うのではと思うのですが
それを、個人レベルでしっかりと確信した瞬間から
自我防壁が、どんどん変化していきます
さて
フロイトは自我防壁が変化するということにも言及していますが
その中でも「昇華」という防衛について語っています
フロイトの言葉でいえば、
昇華は防衛機制の一つで、衝動や感情をそのまま抑え込むのではなく、
別の高次な表現や創造へと変換する働きです
怒り → 表現・正義感・行動力
苦しみ → 芸術・祈り・他者への共感
哀しみ → 慈しみ・まなざし
つまり自分の中にある固着してしまった防衛が苦しいものとなってしまったとしても
壁を壊すのではなく
それが何か新しい形へと変わっていくということが
あるのです
仏教的な言葉で置き換えると
『煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)』という有名な言葉があります
苦しみや執着は、そのまま智慧や慈悲に変わりうるという意味です
自我防壁を打ち壊すのではなく、その素材を光へと錬成する道が
あると
フロイトとユング、そして東洋の思想も指し示しているのです