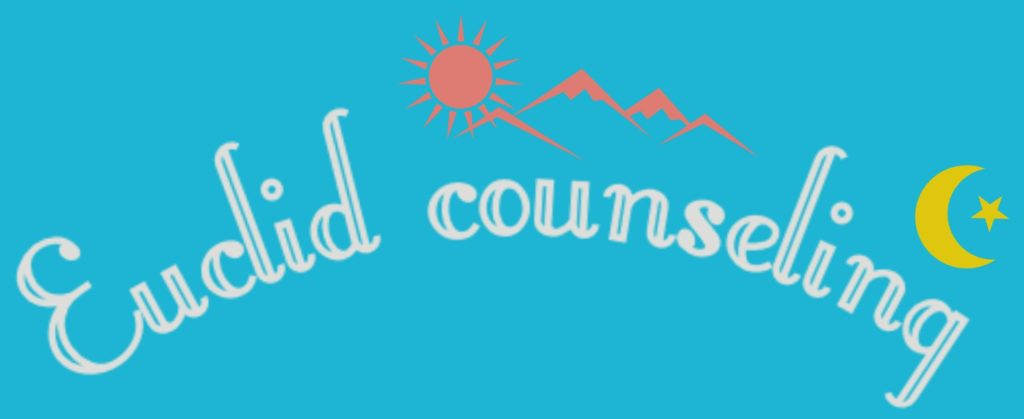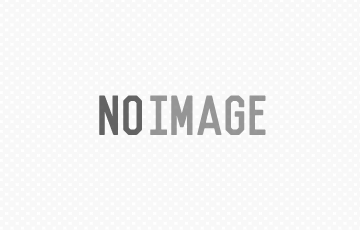恥についての考察
『恥とは、それはつまりトラウマなのです』
と、スーパーバイザーが言っていたけど
私たちは本当に多くの『恥』に囲まれて生きているものだなと感じるのです
私たち、日本人が感じやすい『恥』として
『周囲との差異』をあらわにしてしまうことへの自分への恐怖をともなう感情が
多くにおいて『恥』と言われているような気がします
『他人と違う』ということへの恐怖
が
『恥』としてまずは挙げられます
昔の日本の『恥』では
社会的な規範や集団の一員としての『立ち位置』を重視して
社会や規範、集団のことを『傷つけないポジション』を心の中で守り続けることが
大切だという文化でもありました
たとえば『一家の恥』とか
『恥晒し』・・なんていう言葉は
属している集団を汚す(貶める)ことになるなんていうことで
とても禁忌されていたわけです
1人の行動が、属している集団の個性を表すというもの。
だから『1人1人の行動が規律が取れていて、模範的である』ということが
とても尊ばれた文化でもありました
ーーーーーーーーー
一方の西洋派といえば
日本が『恥の文化』とすれば『罪の文化』とも言えるかもしれません
『罪の文化』の頂点に君臨するのは『神の存在』です
神は絶対的な存在で
神の意志に背く行動をとった人物は
『罪深い』として断罪されます
絶対的な神は『常に心の中に介在していて』
神の意志に背く行動をとった場合に痛むところは『良心』となります
日本が『集団』の中での、自分のポジションをいつも考えているのに対して
罪の文化をもつ西洋圏では
『神に逆らう行動』というのをキャッチするのは
『自分の良心』であります
なのでいつも常に『神との対話』で自分自身の行動を決定するという側面があります
『神は喜ばれるか??』
『神は祝福されるか??』
という
『一対一』の関係性が結ばれているところが『罪の文化』でもあります
ーーーーーーー
カウンセリングをしていると
その、どちらの部分に引っ掛かっているか?ということが非常に重要になってきます
『集団』なのか『神』なのか
精神分析的に
幼少期からの心の発達を絡めて見ていくと
どうやら現代の日本では
そのどちらもが当てはまるケースがとても多いような気がします
心の中に『恥』と『神』の二つを内包している人がとても多いことに驚かされるのです
日本の『神』の特徴として
『八百万の神』(いわゆる神社)と『仏教の仏』がおりますが
どちらかというと
神社の神様は土着の神様で、自然崇拝に近いものであります
良心とは無関係の概念をもつ『八百万の神』は
天変地異を起こし、時に生贄を求め
『取り引き』に応じてくれる神でもあります
日本昔ばなしなんかを読むと、人間との知恵比べの場面なんかも出てきたりする
非常に『地続きなポジション』の神様です
また伝来した仏教の中での仏も
日本での捉え方としては『導いてくれる仏』でもあります
面白いなあと思うのは
『厄除け』の文化です
身体や心を崩しがちな年齢のことを厄年と言ったり
人との関わりの中で憑いてしまった厄(災い)なんぞを
神様(仏様)が取り払ってくれるシステムです
『悪いこと(災いや禍い)』に対して
僧侶(これは神様へお願いをする橋渡し的な人)がお願い(祈願)をして
協力して取り払ってくれるシステムが在るということ。
僧侶の方たちがいくらご祈願をしても
もちろん、採用されない祈願もあるけれども
純朴なお願いごとは
仏教の神様たちはおおかた、願いを聞き留めてくれて
神様たちのネットワークでもって
流れを変えてくれるということがあり
流れを変えてくれるということがシステムとして存在することが
面白いところです
西洋の神様も同じようなシステムがあるか・・というところですが
少し違うところがあって
『神』は『神』を嫌うところがお存りなるのか、
『神への忠誠』が
『神』が一番気にされるところなのかなと思ったりもします
いわゆる日本でいう『信心深い』というよりも
『神に背かない』という絶対的な忠誠心の在処で
神との関係性が出来上がってくるのかもしれないとみております
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
一神教
よりも
多神教の方が、精神的には安定するような気配も見受けられます
何より『排他的』にならないというメリットもありますが
精神分析的に申せば
『唯一』の者を追い求めていくと
精神はバランスを取るのが難しいものなのです
『中庸(チュウヨウ)』という言葉がありますが
* かたよることなく、常に変わらないこと。過不足がなく調和がとれていること。また、そのさま。「—を得た意見」「—な(の)精神」
* アリストテレスの倫理学で、徳の中心になる概念。過大と過小の両極端を悪徳とし、徳は正しい中間(中庸)を発見してこれを選ぶことにあるとした。
(コトバンクより引用)
この中庸の大切なポイントは
『自分自身』で『その中庸』を求める
ということにあります
何かにとらわれずに
何かに肩入れせずに
ただ『すべてが在る』ということを常に思う
という状態こそが
心の一番の安寧につながると、それこそギリシャのアリストテレスの時代からも
言われていて
そして仏教でも『禅』などの修行で
『ただ在る』ということを体感していくということこそが大事だと言われています
そこには『恥』だとか
『罪』だとかの『とらわれ』が無い状態です
ーーーーーーーーーーーー
カウンセリングで、よくクライエント様からお聞きするお悩みとして
『自分の中の白黒思考が辛い』というものがありますが
これも実は
『恥』や『罪』と大きく関わっているところです
『恥』や『罪』を恐れるあまりに
それらを抹消して、『善くあろう』とする働きが
ネガティブに働くと
シーソーのどちらかに負担がかかるように
身体に緊張をもたらし
神経に負担がかかるようになります
禅などを体験された方はお分かりになるのではと思うのですが
実際に深い瞑想状態になると
そこの場所は『善とか悪』とかではなく
ただただ『どんな自分でも周りと繋がっているのだ』という安心感が
もたらされます
でも、実際の社会は
『善や悪』、『恥』や『罪』を指定しないと
機能しないという恐れがあるからなのか
どうしても、『なんか断定できるもの』を欲してしまうのかもしれません
Instagramはじめました カウンセリングルームの様子を よかったらご覧ください